ある晩春の休日、いつもは西に向かう散歩道を東に取った。青梅街道を新宿に抜け、更に靖国通りを飯田橋まで歩いた。靖国通りは丁度、都営新宿線の真上を歩くことになる。曙橋駅を過ぎた辺りだったろうか、ギョロ目で、でっぷりと太り、はだけたワイシャツ姿の男が、暑苦しそうに沢山の書籍が無造作に詰まった鞄を肩に掛け、更に原稿のゲラと思われる大きな封筒を両手に抱えてコンビニに入る姿を目にした。擦れ違って、何処かで見た顔だあなぁ、…と思っていたら、ラスプーチンこと佐藤優氏であることに気が付いた。この辺りに仕事場があるらしい。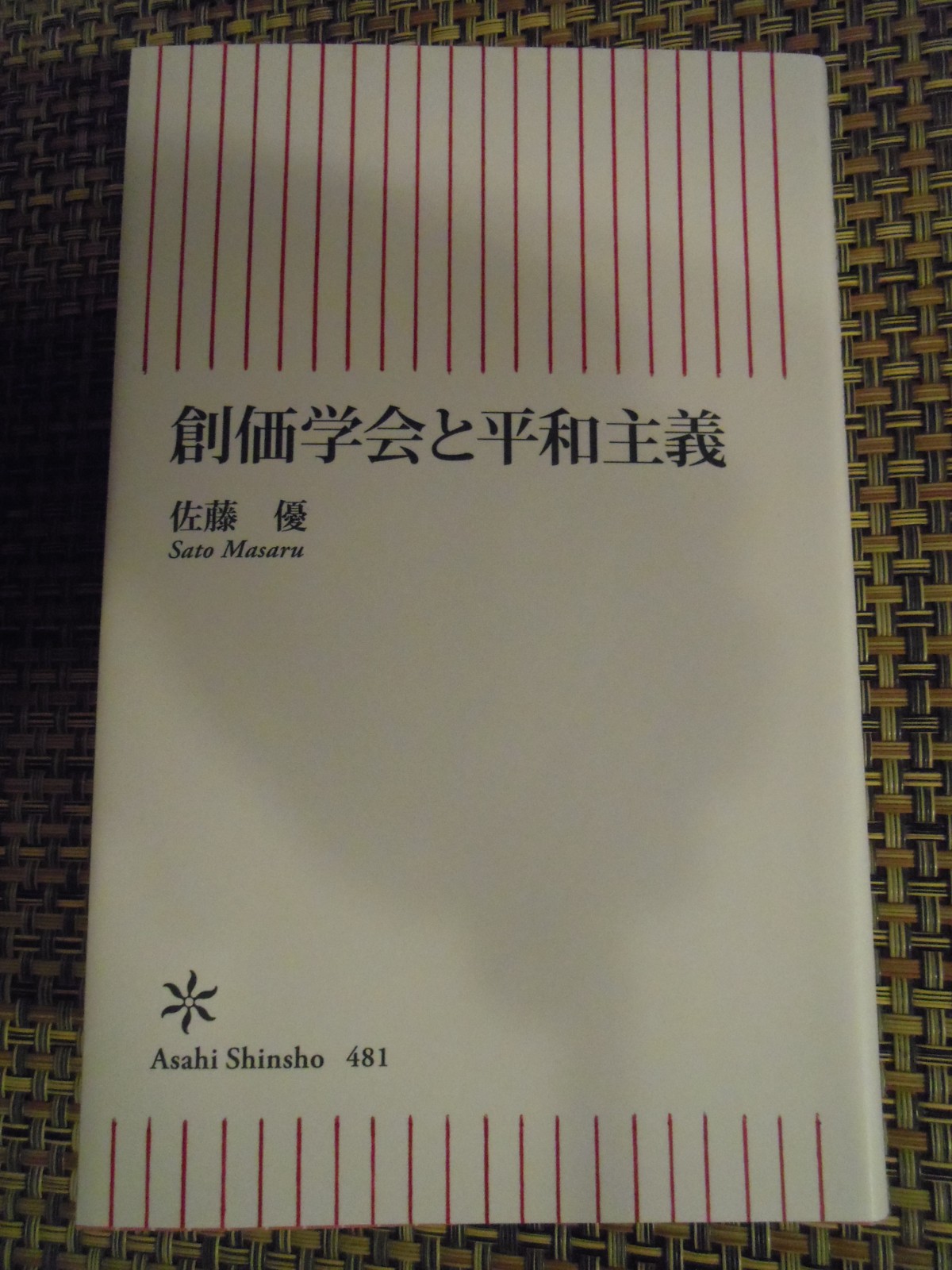
ベストセラーには余り関心はないのだが、この本 『創価学会と平和主義』(朝日新書)は思わず手にとってしまった、という人も少なからずいる筈だ。何故、プロテスタントの佐藤優が創価学会を書くのか、しかも、「集団的自衛権を骨抜きにしたのは創価学会の平和主義だった」という帯も気になる。これが「気になる」こと自体がひとつの社会現象なのだ、ということが分かるのは読後あり、だからこの本がベストセラーとなるのだ、と納得がいく。
「宗教社会学」として読むと面白い本だ。創価学会の宗教的支柱となっている日蓮宗には「此岸的救済」という特色がある。浄土宗のように過去の因果で現在があるのではなく、現在の因果で死後の未来が拓ける。だから現世(此岸)で価値を創りだす努力を求められる。従って、現在という逆境の中でも決して教義(南無妙法蓮華経のお題目)を捨てることはない。戦中の神道による国家統制に抵抗し獄死した初代会長 牧口常三郎と、これを轍とし戦後の平和主義の礎を築いた二代目会長 戸田聖城を経て、池田大作氏は創価学会の教義を確たるものにしていく。
もうひとつ重要なことは、日蓮が被った社会的迫害(「法難」)への対処方法が現在に生きていることだ。彼とその弟子たちは「折伏」(しゃくぶく=徹底した議論)による仏法への帰依を解くが、同時に逆境より逃避することなく常にこれに対峙することが求められる。こうした背景があるからこそ、公明党は集団的自衛権を強行しようとした安倍政権に留まり、普遍性のある平和主義により「実質的にこれを骨抜きにする」ことができた、という論旨である。
佐藤優がこの事象に着目するのはプロテスタントとして、「現代日本の危機」にいかに宗教的に対峙すべきか、という深い問題意識があるからである。彼が学んだ同志社大学神学部の教授たちは、戦中、国家権力に「転向」したキリスト教を戒めるために、彼等に牧口、戸田の徹底した抵抗を諭したという。つまり戦時国家に対峙しうる社会変革の「現世的実現」の力を宗教は貫くべきだ、という教えである。それを、創価学会は「体制内」にある公明党への影響力のもとに実現した、と語っている。
社会学的に非常に興味をそそられたのは、佐藤優が「創価学会は中間団体(権力の暴走を抑止する国家と個人の間に存在する組織)」である、と看破していることである。近代化の中で伝統的共同体が崩れるとともに、家族主義的経営として企業に引き継がれた中間団体は、やはり企業内から消失し、今の日本はその組織的基盤を喪失している。その中で普遍的な(つまりナショナリズムに偏らない)平和主義を標榜する「中間団体」としての創価学会の機能に注目しているのである。現代日本には、政治意識が中道左派にある国民の利益を代表する政党は、公明党以外に存在しない。
佐藤優は「あとがき」に最も重要なことを書いている。現代の日本人は無宗教だと言われるが、ロシアの宗教学者が言う「無神論という宗教」に類した「宗教」に染まっている。それは自らが作りだした「拝金教」「出世教」そして「ナショナリズム」であり、愚かなことにこの人造宗教に振り回されている。創価学会の平和主義の研究は、現代日本人が無意識の内に抱いている転倒した宗教を脱構築してくれる一助になるのではないか、と言う。
なかなか、時宜を得た、そして宗教と外交に深い造詣を持つ佐藤優ならではの論考であると思う。おそらく、この本は今回の衆院選に少なからず影響を与えるに違いない。
それにしてもあの晩春の昼下り、佐藤優氏はコンビニで一体、何を買ったのだろう。



