地下鉄東西線・早稲田駅を降りて大学と反対側に向かうと「夏目坂」という坂がある。漱石・夏目金之助が生を享けた、牛込馬場下の名主、夏目家屋敷に因んでこう呼ばれた。坂下には今も「漱石生誕の地」の碑がある。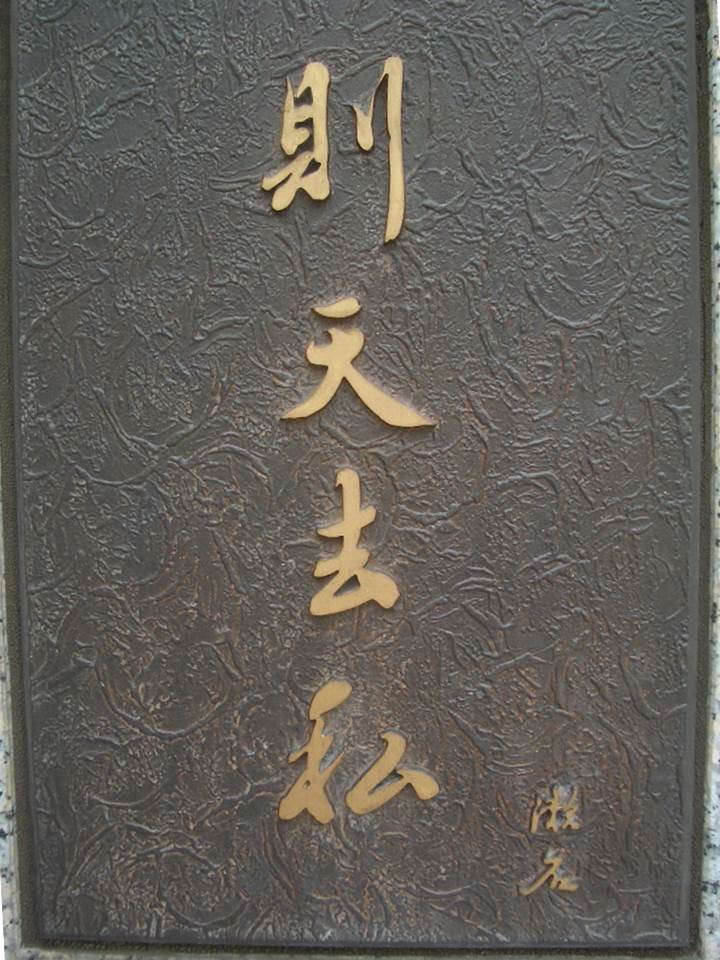
短く急峻な坂を登り切ると右手に「来迎寺」という浄土宗の閑静な寺がある。江戸期より続く古刹である。十年前、門前のソメイヨシノが春風にはらはらと散る頃、父はこの寺の墓所に葬られた。生前自らが建てた墓である。
父は青森県南津軽郡浪岡町の出身。万事につけて世話好きで、晩年は同郷出身の力士の谷町や来迎寺の檀家の世話役など幅広い交際をしていた。県人会ならぬ「浪岡会」なる同郷会の幹事を引き受けていたことから、没後三ヶ月、この「浪岡会」に、父の偲ぶ会を開催していただき、母と呼ばれ雛壇の上に祀り上げられた。その会の、お開きの挨拶の原稿が残っている。
本日は皆さまご多用中にも拘わりませず、亡き父良輔の偲ぶ会にお運びいただき有り難うございました。また、会長の〇〇様や〇〇様をはじめ幹部の方々には、このような会を催して頂き、心より感謝しております。父もあの世でさぞ喜んでいることと思います。このような高い席より失礼とは存じますが、家族を代表してひとことご挨拶申し上げさせて頂きます。
早いもので、父が亡くなりほぼ三ヶ月が経とうとしています。晩年は、心筋梗塞や大動脈瘤など循環器系の病気で入院することが多く、皆様にもいろいろとご迷惑をお掛けいたしましたが、最後は胆管の癌がもとで肝不全となり、四月十三日に七十六歳で帰らぬ人となりました。度重なる入院の際には、浪岡会の多くの皆様にお見舞いを頂き、本当に有り難うございました。
父は昭和二年十月に、浪岡に生まれました。昭和十五年に浪岡尋常小学校を卒業し、できたばかりの旧制の市立一中、現在の青森北高に入学いたしました。昭和二十年三月、終戦を迎えるその年に、東京外国語専門学校、現在の東京外国語大学のロシア語学科に入学しますが、それまでの十八年間を浪岡で過ごしたことになります。昭和二十四年に外大を卒業後も就職難で一時帰郷し、昭和二十七年に再び上京して東京大学出版会に入社いたしました。
こうして二十年余りを過ごした浪岡に対して、東京で生まれ育った私自身は、夏休みなどでたまに帰省する程度で、余り親しくは接して参りませんでしたが、父は尽きせぬ望郷の念を強く抱いていたように思えます。私の免許証には、父の厳命により、未だに「浪岡町 大字吉内 字東留岡」という私の本籍が記載されています。そして、まさにこうして、浪岡から上京されてご活躍されていらっしゃる皆様とご交誼を結ばせていただいていたことも、望郷の念に支えられたものに他ならない、と思っております。
言い古された言葉に「故郷は遠きにありて思うもの」という詩の一節があります。そして、故郷を精神的な支柱としながら異国の地で生活する「故郷喪失者」という言葉があります。詩人や文学者の多くが、こうした「故郷喪失者」としての心境を作品に残してきています。父も、そうした故郷喪失者の一人であった太宰治に、若い頃心酔していました。おそらく、父も、言葉は適切ではないかもしれませんが「根無し草」であったが故に、逆に何者にも囚われることなく、寛い心を持つ自由人たりえたのではないか、と思います。欧米では「コスモポリタン」といいます。二十世紀初頭に、株の仲買人というサラリーマン生活を捨てて南国の楽園で作品を創作し続けたポール・ゴーギャンや、彼を『月と六ペンス』で描いた、イギリスの作家、サマセット・モームなどは、こうしたコスモポリタン、つまり故郷喪失者たちでありました。
実は私自身も、93年から六年半の間、社命でニューヨークの駐在員生活を経験しました。この時に感じ続けていた日本への郷愁は、まさに、上京後の父が故郷の浪岡に感じ続けていた郷愁に他ならないと思っています。父の葬儀の際に、アメリカのコロラド州より一通のお悔みのEメールが英文で届きました。父が出版会に在職中、国際出版局というところで働いていたアメリカ人女性の編集者ですが、成田さんの日本語は津軽訛りで分かりにくかったけれども、アメリカ人の私にも分け隔てなく優しく接して頂いたことを今でも深く感謝しています、という内容でした。私はこれを見て、父が、境遇や立場を超えて、そして国籍や人種さえ超えて、誰に対しても分け隔てなく優しい思いやりのある姿勢で接し続けてきたこを、改めて痛感したわけです。
そうした父の人生哲学は、おそらくは、父の故郷である浪岡で育まれたものだ、と思います。そして、ニューヨークから日本を思い続けていた私自身の望郷も、きっと浪岡に行き着くことになるに違いありません。本日、こうして浪岡会の皆様に偲ぶ会を催していただくことは、父にとって本望だと思います。皆さまの父を偲ぶお気持ちを、「誠実」という言葉を愛した父の人生哲学とともに、これからの皆様のこころの中で大切にしていただければ、家族としても、これに勝る幸福はございません。
本日は、このような会を催して頂き、本当に有り難うございました。簡単ではございますが、御礼の言葉に代えさせていただきます。
あれから丸十年が過ぎ去った。父の背中は、いまも夏目坂を登っている。



